【 食育 】20代に知って欲しい食の大切さ【 お店でも取り組みます!】

『 日本の外食は安い 』
これは日本を出たことのある人は感じたことがあると思います。
¥500 あればお腹いっぱいになれるなんて異常と思う方も少なくないと思います。
これは企業努力の賜物なのですが、一方で素材を作っている方 ( 具体的には野菜を栽培している農家さん ) にしっかりと成果に見合った価格で取引されているのかはまだまだ不透明な部分もあります。
これからの時代は食品の作り手や流通が明確であるもの、そして循環する無駄のない仕組みや取り組みはきっと注目されるようになると思います。
そして、それに関わる全ての方に正当な成果が渡るようにもなると思っています。( なって欲しい! )
少しわかり難くなるのですが、【 トレーサビリティがしっかりしていてサスティナブルでフェアトレードである 】と言い換えることができます。
もしそれが当たり前の時代になれば今の日本の食文化である【 安かろう 】はなくなり、良いものにはしっかりと値段がつけられるようになると思います。
そうなれば働く方の賃金も上がるはずですし、能力のある人はもっと評価されるようになるはずです。
そのためにまずは『 いいものとはどんなものなのか? 』をたくさんの人が知る必要があります。
特にそれを担ってるのは僕たちを含めた若い世代が良いものを知り、評価し、後世に伝えていくことが必要です。
【 食育 】と一口で言ってもいろんなアプローチがあって、たくさんの意見があると思うのですが、僕は以上のことがイメージできています。
この記事では、そのイメージできていることを具体的にシェアするのと、お店で取り組もうとしていることをご紹介させていただきます。
良いものには正当な評価をするようにしよう!
この記事をきっかけに良いものを知ろうとする方が増えて、良いものにはそれに見合う評価がする人が増えたら良いなと思っています。
この記事を書いている僕は、海外生活を2年経験しています。
カナダのバンクーバーで1年、オーストラリアのメルボルンに1年。
英語は全く話せませんでしたが、一念発起で脱サラしワーキングホリデーに挑戦。
2ヶ国目のメルボルンでコーヒーに出会い、その文化に魅了され、
現在は日本でコーヒー屋を営んでいます。
旅行を含めたら数カ国に行った経験があるのですが、毎回思うのは日本の外食は安いなと。
スペシャルティコーヒーに携わるようになり、トレーサビリティやサスティナビリティ、フェアトレードに目が向くようになり様々なことに取り組んでいます。
良いものがしっかりと評価されるようになれば、国民の幸福度は上がる
こんな方に読んで欲しい
・食育に興味がある
・日本の外食は安すぎると思う
・トレーサビリティって何?
・サスティナビリティって何?
食育とは

食育とは
様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることである。2005年に成立した食育基本法においては、「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけられている。
引用 : Wikipedia
まず、定義を調べてみました。
いかがですか? 正直僕は食育基本法なる法律があることは知りませんでした。
基本的には『 経験 』が鍵になってくる言葉だということが、この定義からわかります。
食に限らず経験って大事ですよね。
何事も経験しないとわからないことばかりです。
いくら知識があっても経験したことないとできないに等しいですし、経験のない人の言葉にはなんの説得力もありません。
それと同時に『 経験できる環境 』が大切です。
経験しようと思っても、経験できる環境や場所がなければ経験できないですからね。
食にフォーカスすると、良い素材を美味しく調理されたものが食べることができる場所が必要になります。
今の日本にはこれはあります。たくさんありますよね?
ではなぜ、食育が必要だと考えられているか?
【 安いものが多すぎてそっちを選ぶ人が大多数であること 】が原因だと思っています。
本当に美味しいものを経験する前に、安くてそれなりのものを経験してしまっているので、後者が増え前者が増えないんだと思います。
良いものを知ると、その先にまで興味を持つ人が増えます。
この美味しい食べ物はどう調理されたのか?素材はどこの誰が作ったものなのか?どこで栽培されたものなのか?
これこそがとても大事なのかなと思っています。
以上のことが、後に述べる『 お店での取り組み 』を考えるきっかけになります。
トレーサビリティとは

トレーサビリティ(Traceability)とは
トレース(Trace:追跡)とアビリティ(Ability:能力)を組み合わせた造語で、日本語では「追跡可能性」と訳されます。自動車や電子部品、食品、医薬品などの業界によって定義は多少異なる。
トレーサビリティが確立できていると、たとえば出荷後の製品に問題が発生した場合、部品(原材料)の使用実績にさかのぼって調査して原因を究明し、同様の問題が発生する可能性がある製品を抽出することができる。
引用 : トレーサビリティ大学
こうやってみると横文字よりわかりやすいですよね?
要は、その商品はどこの誰がどのようにして作ったもので、どのような経緯でここまで辿り着いたかが追跡ができるようなものってことです。
これがはっきりしているものが増えてきてはいるものの、まだまだ不透明なものが多いのも事実です。
トレーサビリティには2種類あります。
内部トレーサビリティ
簡単にいうと、『 消費者の手に渡る前までの追跡可能性 』のことです。
その製品が1つの会社内で生産されているのであれば、社内で誰がどのパートでどの工程を担当し、どの部品を作ったかを明確にすることを指します。
自動車のように何社かの手に渡って作られているのもこれに当ります。
どの会社の誰がどの部品をどこで作ったのかを明確にすることを指します。
チェーントレーサビリティ
生産から小売 ( 消費者 ) までの複数の段階で製品の移動が把握できる状態を指します。
一般的に言われるトレーサビリティはこれに当ります。
コーヒーももちろんこれです。
コーヒー農園の生産者からお客様が飲むコーヒー1杯までの流れが、このチェーントレーサビリティです。
サスティナビリティとは

サスティナビリティとは
『 持続可能性 』のことを指します。
持続可能性とは、一般的には、システムやプロセスが持続できることをいうが、環境学的には、生物的なシステムがその多様性と生産性を期限なく継続できる能力のことを指し、さらに、組織原理としては、持続可能な発展を意味する
引用 : Wikipedia
環境問題について話される時には必ずと言って良いほどこの言葉が使われています。
もっと砕いてわかりやすい言葉で表現すると、【 無駄がなく循環するもの 】です。
「 1度使ったら燃やして終わり 」ではなくて、100%リサイクルできたり、他のものに代用できたりするものがこれに当ります。
例えば僕の営む AERU COFFEE STOP で使っているサトウキビストローは、1度使ったら繰り返しは使えないけれど堆肥を作る材料となり得ます。
具体的には、農家さんは家畜の糞にいろんなものを混ぜて堆肥を作るのですが、その混ぜるものの1つに木屑があります。
この木屑はお金を出して購入しているところもあるようですが、このサトウキビストローはその木屑の代用ができます。
もっと言うと、ストローを使う前の製造段階の話。
原材料はサトウキビの搾りかすです。
本来捨てるだけのものを利用価値の高い製品へと生まれ変わらせています。
循環してますよね?
これこそが持続可能な製品ということです。
ストローを作るために新たな原材料を使うのではなく、本来捨てるはずだったものを使うんです。
環境に優しいのはもちろんの事、限りある資源を使わないということは未来を守ることになります。
素材や製品だけではありません。
あなたのマイタンブラーを持ち歩くというその1つの行動も、未来を守る行動、【 サスティナブルな行動 】です。
AERU で取り組もうとしていること

ここで1つ AERU COFFEE STOP で取り組もうとしていることを紹介させてください。
冒頭で話した【 良いものを知ることのできる環境 】のお話です。
若い時から良いものを知ってもらうことで、この先良いものを知っている又は知ろうとする人が増えると思うんです。
でも学生の時って自由に使えるお金ってそんなにないから、値段の高いのもを多く経験できない方が多いですよね。
そこで AERU ではコーヒーの学割を始めようとしてます。
学生の時からスペシャルティコーヒーに触れて欲しい。
コーヒーは苦くない、コーヒーはフルーツなんだということを20歳くらいから知って欲しいという想いが強く、これに取り組むことになりました。
もちろん高校生の頃からでも早すぎることはないと思っています。
高校生には学割されたところでコーヒーにかかる金額としては高く感じるとは思います。
でも、今より手を出しやすくできるのかなと思っています。
具体的な金額等は今後どこかのタイミングでしっかりと SNS でお知らせします。
「 AERU があるからこの街に住むことにしました 」
そんなこと言ってくれる若者が出てきたらおじさん泣いちゃいます。笑
まとめ

いかがでしたでしょうか?
食育というワードをきっかけに、いろんなことにおいて『 良いものを知る 』楽しさを知って欲しいなと思います。
例えば食べたことのない美味しいものを初めて食べる時、とってもワクワクします。
例えば飲んだことのない美味しいワインを初めて飲む時、とってもワクワクします。
しかし、そこには金銭的なハードルが存在します。
全員に対してそこを取り除くのは難しいし、それをやってしまうと良いものには正当な対価をつけるフェアトレードの観点で崩れてしまうのでできません。
ですが、勉学に励む学生に限定してそのハードルを下げる取り組みは既にいろんなところでありますよね。
若い頃から良いものに触れることで、30歳になってからの生き方も価値観も変わると思うんです。
物で溢れている日本ですが、安ければいいという思考は若いうちからなくして欲しいなというのが僕の本音です。
実際のところは難しいんですが、良いものには正しい対価をつける意識は持っていて欲しいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!


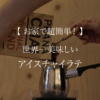


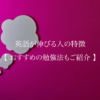



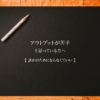
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません